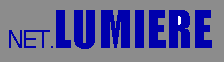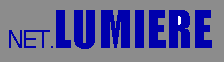|
(スタッフ)
製作=東映
企画=俊藤浩滋 吉田達
助監督=澤井信一郎
撮影=林七郎
音楽=菊池俊輔
美術=藤田伝
録音=広上益弘
照明=川崎保之丞
編集=田中修
|
(コメント)
○今回のシネマ・ジャックでの「男優・女優」のシリーズでは、心待ちにしていた反面、おもしろくなかったら、どしようか、見るのは、止めておこうかなんて考えたりして、でも結局出掛けていった。本当に30年ぶりだからな。何カ所かカットが抜けたり、カラーなどの発色難やフィルムの傷はあったが致命的ではなかった。
まあ、これほど、慎重なものいいになるのは、日本映画のなかで、優れた映画の一本だろうと思っていたわけだが、当時の印象は、残念ながら、記録では残っていない。十九歳になった頃だし「映画作家」でもあった。傑作だと喝采していたと思う。
○山下耕作「博打打ち・総長賭博」(68)、加藤泰「明治侠客伝・三代目襲名」(65)など傑作なやくざ映画の中で、マキノ雅弘監督が見せたやくざ映画の世界も、独自に輝いていた。「おんな心の想い」をせつせつと描きながら、男の生きる道を「やくざと堅気」を対比して迫る感動的な話しを、映画として語って見せる。
○ここでのマキノ作品の特徴は、ワン・シークエンスごとにあるテーマをきちんと語り尽くして、次にいくというようにできていることだ。賭場が開かれている大きな邸の門構えと白塀が遠くに見える。なかには、高倉健の花田秀二郎が、ハンチングを被り、痩せて、顔を薄汚くした野良犬のように、賭場に座っている。怪訝な表情をしながら、「半」とはる。丁と出て去る。外に出ると、ツボふりの山本麟一とその仲間に、追われ、殴られる。中途半端ないかさまの疑いをなじり、勝負は、「見破られて、手を落とされる」かの真剣勝負だといわれる。花田は、よろけながら、大きな銀杏の木の下に、降ってきた雨も避けるように、座り込む。そこへ、芸者の卵の藤純子が通りかかる。彼女は15歳という役どころで、純真な少女を演じて見せる。高倉健もこどもっぽく見える。ここでのふたりのやりとりを当時は「いいね、いいよね」といいあったのだと記憶している。今回見ても、ここの話しにのれるかどうかで、この映画の評価が違ってくる。藤純子は、大きな銀杏の樹の下に、傷ついて、倒れている男を見て、どうしたんだろう、気の毒にと、近づく。「血が出てるよ」「この酒で拭くといいよ」「寒いだろう、これ飲むと暖まるというよ」と、酒を買いにいった帰りにだった藤純子は、減ってしまった酒にやっと気づいたように、「おかみさんに叱られる」「キセルで叩かれる」と言う。「叩かれの、がまんすればいい」、「おかみさんに頼んで、泊めてもらおう」とまでいって、傘を置いて駆けだしていく。おかみさんにかけあう藤純子、電信柱の影で覗いている高倉健。やっとのことで、了解をもらって、銀杏の樹の下に駆けて戻る藤、そこには、もう居ない。雨に撃たれれている傘。まあ、こんな始まりで、3年後と展開する。
○この映画では、藤純子の台詞、動きにすべて無駄がなく、マキノ監督の映画における「女性」像の集大成ということもいえる。思い出すだけあげてみると、次に、(1)刑期を終えて出てきて、後見人の「親分」の粋なはからいで、芸者になっている藤純子たちをお座敷に呼んで再会するシーン。銀杏の樹の下の男だとわかったところで、着物のたもとを両手で持って顔て顔を隠して照れる。なれそめを仲間の芸者衆に聞かれ、話しはじめる。「もう、いいでしょ」と高倉にいわれるまで、喜々として話す。夢中になる純真さと高倉への思いが伝わるシーンだ。おまけに年増の芸者が、藤に、高倉の手を取らせ、男と女の道行きを演出し、見送る。ふたりが、外に出るとまた雨。(2)高倉の勤める「喜楽」に呼ばれて、嫌な客を相手して、言い寄られるのを拒み、高倉たちも加わって、立ち回りになるシーン。(3)高倉の着物を縫っているシーン。「これは、ひとりで縫いたいの」(4)「わたしの手をやってください」と高倉をかばうシーン。「喜楽」の座敷に上がり込んできて、訴える。(5)できあがった着物を着せたいと誘いにきて、照れる高倉、「いってこい」快く送り出す池部、からかう長門とのからみ、新しい着物に袖を通す。祭りの出店を見て歩くふたり、はやり歌を口ずさむ藤が、高倉のあとをついて来る。「この着物を、みんなに見せてくる」と高倉。「待ってるから、早く戻ってください」と藤純子。(6)殴り込みを見送る。7ラスト、上半身裸の高倉が、警察に連行される、人だかり。藤、着物を掛けてやる。ここで、なんて声を掛けたか聞こえない。大立ち回りの負傷と憔悴そして、返り血、「背なで泣いている唐獅子牡丹」。すべてが、高倉健が自らが、生き方を問われる場面の「きっかけ」に絡んでいて、高倉と「映画」にうまく寄り添っていることがわかる。
○高倉は、もともと高級割烹「喜楽」の跡取り息子でありながら、若気のいたりで、やくざになっている。父親も、跡を継いだ妹も「関東大震災」で死ぬ。震災後、後妻の盲目の母親と妹婿が店をやっているが、この婿が壊滅した「喜楽」をもっと大きく復興させようと「相場」に手をだしてては、借金を増やし、敵対する組に借りをつくってしまう。
○この「喜楽」板前として働く、池部ももとやくざである。高倉の事情も知って、盲目の母には、息子だということを伏せて、板前として働かせる。この背後に、父親と親しかった「やくざの親分」がいて、すべてがその人のはからいであり、藤との再会も、この「親分」の粋な配慮である。やくざから足を洗って、堅気として、真っ当に生きたいとする人間に、昔の因縁をすてさせてくれない事情が、向こうから舞い込んでくる。映画はもうやるしかないというぎりぎりの選択で、池部が始動し、高倉が追い、「ここは、堅気の出番じゃない、おれに任せてくれと」高倉が止めるが、ふたりの「殴り込み」というシーンに向かっていく。この行動は、すべて見ている人を十分に納得させる「男の美学」である。そして、高倉健には、「静」の演技から、「動」への演技への転換の妙と、立ち回りは、見るものに大いに期待させる「華」がある。これは、渡哲也にもあったが、高倉健にもある。映画スターが共通して持つ「華」であり、そのスクリーンにしか存在しない魅力なのだと思う。最後に、マキノ演出は、先ほどの藤純子の演技に、最近見た「丹下佐膳」の山本富士子などや「人生とんぼ返り」の左幸子など芝居に共通した「うまさ」と型にはめていく「人情」の機微が伺える。(2001.2.25)
|
(キャスト)
高倉健
池部良
藤純子
荒木道子
中村竹弥
長門裕之
公開年月日:1970.9.22
映画館:横浜シネマ・ジャック「日本映画大全集Part2」「男優と女優」
|