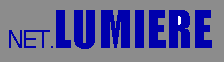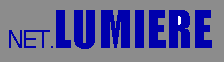|
(コメント)
○はじめは、映画の中の時間の流れに奇妙な遅さが稚拙な表現にもとれるので、見ていて少し苛立つ。次第に、この主人公が死を間近にしている青年であることがわかるのだが、まだここで納得するまでにはいかない。病気で余命幾ばくもないという設定に安っぽい「感動」も危惧されるわけでちょっと困ったなあというのが当初の感想だ。
○しかし、親父がやっていた古い写真館を息子が機械化して引き継いだという設定から駐車違反を取り締まる若い婦人警官との出会いなど、死を意識してのナレーションと映像が展開する。そして映画は小学校の校庭での思い出や友人たち、写真館の客、そして父と妹の家族感と過不足なく描いていく。うまいなと思わせるところに出会う。
○それは、夜、布団をかぶって泣き出した息子の部屋まで近づく父親の影が戸を開けそうになるが開けないで戻る。息子の死を受け入れざるを得ない諦念が映像で語られているというシーンあり、
もうひとつが恋人の関係が芽生えた若い警察官に入院の事情を説明するためか、警察署まで訪ねるが会えない。あきらめたところで休んでいる喫茶店の窓越しに駐車違反を取り締まる彼女が見える。声が掛けられない、声を掛けてはならないという抑制と愛おしさの表現として窓に遮られている大写しになる主人公の手と先にいきいきとして路上で働く彼女が重なるというシーンである。
これらは、映画は映像で語るものだという方法意識が監督に明確にあることを示している。
○彼女に主人公の病気も死も知らせないことで(父親の諦念もあわせて)安っぽい感動から崇高な映画へ昇華させることに成功している。彼女がだんだん綺麗にっなていくのがいい。(2000.7.4)
|