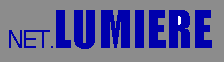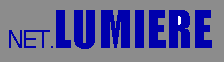|
(コメント)
○戦後を生きてきた日本人(庶民)の背景には、「農村」という「ムラ」的社会を支えた女系社会が厳然としてあり、日本人の誰もが、その影響下にある。
驚くのは、きっといまだに現代においても払拭しきれてはいない。ハンセン病の扱いなどにあるように、内なる差別の根源として「天皇制」を遺制とし残す日本社会には、建前と本音の使い分けや総論賛成、各論反対などと一筋縄ではいかない。本当のことをしっかり言っていくことを積み重ねるしかない。
○確か直木賞作家の野坂昭如のこの作品を「誰が映画化するのか」という話題性の中で、やはり、野坂が今村がいいと決めたということだったのだろうか、ここらは、はっきりはしない。
○さて、映画だが、当時も見ている。映画全体について明確な感想を残してはいない。ただ、坂本が狂っていく場面は強烈に印象に残っている。あらためて見て、まず、今村の映画への方法について意識的であることは、先日見直した「にっぽん昆虫記」でも言及したが、この映画にも現れている。
○間借り人である小沢と美容院をやっている坂本とは内縁関係にある。坂本は小沢に気を遣い家の名義をあなたものにしてくれと申し出たり、娘の啓子と結婚してくれなどと言い出すなど、小沢に言わせれば、心優しくまじめだから狂ったということになる。
野坂と今村がいいたことは、ここに登場する「エロ事師」たちも人を殺したり危害を加えたりすることはなく、世の中の裏街道を生きざるえない人間に、そのしたたかさに共感しているのだろう。
○殿山泰司と知恵遅れの孫との関係、小沢と継母との関係、小沢と啓子の関係など性的な関係が人間のベースに脈々と流れ、さらに雁治郎まで登場させ、女学生を襲いたくなる欲情を語らせ、小沢が正真正銘の処女を紹介するといって子持ちの女をあてがう。
「エロ事師」商売の面目躍如。ゴダールはこの映画を見て、「汚い」映画と辟易していたという。今村や殿山のユーモアはわかりにくく陰惨でもあり日本的か。
○坂本が狂った病院の窓の手すりに捕まって、眼下に道行く人に、着物をはだけさせながら叫ぶというシーンから荒野に手すりの柵をおいて叫ぶという映像を挿入させるなどという実験的映像も今村映画の世界だ。
映画「うなぎ」にある鰻の水槽に飛び込んで見る役所の幻想シーンは、息子の脚本にあるのかと勝手に思っていたが、これは今村監督自身の世界だということがわかる。坂本の前夫への義理立てであり、鮒が前夫の化身のようにじぶんを見ていると思いこみながら、幻想や幻覚に誘われ、狂っていく。
○小沢も商売よりも、夢の「ダッチワイフ」づくりに没頭し、家の裏に浮かぶ船を作業場としているが、繋いだロープが解けて、海へ流れ出している。これは、今村映画の共通したイメージの一つである。この国を離れ海へ漂う。この国の成り立ちを逆に辿るイメージにも繋がる。
○一方、どうしようもない女子中学生だった啓子は、母親の美容院を継ぐ格好でまじめに働いているというラストになる。人間のしたたかさよ。(2001.7.21)
|