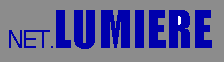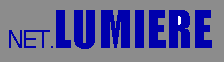|
(スタッフ)
製作=マザーアーク
配給=アルゴ・ピクチャーズ
プロデューサー=鈴木剛
エグゼクティブプロデューサー=諸橋裕
原作・脚本=園子温
撮影=谷川創平
美術=藤田徹
編集=伊藤潤一
音楽=長谷川智樹
特殊造形=西村喜廣
録音=池田知久
助監督=天野修敬
|
(コメント)
園子温の映画を見るのは初めてだが、気になっている監督のひとりで、この「紀子の食卓」というタイトルに何か感じるものがあった。(ケイズシネマ「K'scinema」という映画館に一度は行ってみたいと思っていたこともある。)それに、最終日の前日であることも知って、ここで見ておかないと後悔することになるという予感もあった。(原作(円地文子)は、読んでいたのだが、公開当時見のがしたまま、未見のままになっている「食卓のない家」(小林正樹監督作品)という映画を思い浮かべていた。)
新宿昭和館という古い映画館のあった付近に久しぶりに足を踏み入れる。懐かしく思いながら、「紀子の食卓」の大きな看板と「昭和館ビル」という小さな表示も見られ、そのビルの3階に、めざす映画館「K'scinema」(84席)があることがわかる。小さな洒落た気持ちのいい映画館だ。平日で客は少なかったが、さすがに東京・新宿だけに20人程度の観客はあったようだ。
そして映画は、わたしに衝撃的だった。ここまでやられると凄いなというのが正直な感想だ。青山真治の「ユリイカ」に匹敵する「衝撃」があって、しかも、どの映画にも似ていない、独自な映画世界になっている。この映画は、画面の構図やフレームの切り取り方の個性による静的な映像表現をベースに人物をも風景化し、視線そのもを映像化(抽象化)する映画とは違っている。
どちらかといえば、日常的にありふれた映像から、人物の動きを追うキャメラは、ドキュメンタリー的な動きで対象を捉えて見せる。「ユリイカ」と決定的に違うのは、「惨劇」や「事件」そのものをつくりだし具体的な画面に再現して見せるということだ。それは、「ユリイカ」では寡黙で静寂な画面が画面外の惨劇を語って見せるのに対し、この映画では、映画としてのリアルな画面の力を持たせることに成功している。
この映画における大きな特徴は、軸となる三人の登場する人物(紀子-みつこ)=吹石一恵、上野駅54(クミコ)=つぐみ、紀子の父親=光石研そして、紀子の妹(ユカ-香)=吉高由里子が持つ、それぞれの「現在」にいたる事情について、自分自身が語るという方法が取られていることなのだが、ここに「レンタル家族」を演じるという「役割」を重ねてみせることで、演技という嘘が、役者と見るものに奇妙でスリリングな緊張を呼び込む。
映画は17歳の普通の女子高校生が持った「不満」が、こことはちがう場所へという「希望」の実践として東京へ家出したことから始まる。紀子の行動には、父を初めとする周囲の無理解と「廃虚ドットコム」というサイトへの参加が決定的な役割をはたす。パソコン上に印字された文字と紀子の声も重ねられ、いつのまにか、パソコン画面と他者との繋がりを象徴するシルエット画像から、東京駅から銀座、上野駅54の謎を解くために、上野駅構内を紀子が頼りなげに歩く実写へと変わっていく。ここで最初の衝撃に出会う(上野駅構内のコインロッカーで、実在する「クミコ」に紀子が出会う)。
わたしも、いま、クミコ役のつぐみという女優がもつ繊細な存在感に魅了されている。彼女が演じるクミコが語る「真実と嘘」が、紀子に対し圧倒的に魅了するカリスマ性を発揮し、この映画の凄さを見せつけ、さらに、もうひとつの衝撃であるプラットフォームでの惨劇を紀子に立ち合わせる。このシーンは、はね返る大量の血を浴びせて見せるショットが効いている(ここは、女子高校生の集団自殺を54人をプラットフォームに並ばせ揃って飛び込む寸前を見せる、驚くべきシーンである)。
さらにクミコ=つぐみの衝撃的シシーンとして、「真っ赤な太陽?」「違う。」という会話から、「バラが咲いた」がラジオから流れるホテルでの「惨劇」場面に立ち合うところがある。ここでの意味はわかりにくいが、この集団的の中で死の境地にたっする同志の壮絶な死を真剣に受けとめる。ここもなかなかの見せ場になっている。
父・徹三は、紀子の家出から、妹の香の家出、妻の自殺という境遇から、地元の業界新聞記者という職を辞めて、この紀子たちの謎を解くために、彼女たちの日記など手が掛かりの調査・分析に専念し、クミコたちの「自殺クラブ」と「レンタル家族」に辿り着く。紀子の家出は、現実の家族を崩壊させたという現実ともうひとつの現実以上のリアリティーを持つヴアーチャルな世界へ父・徹三を呼び込んでみせることになる。
紀子は、納得できないことがあると、家族みんなが夕食を済ませたあとにも、じぶんだけの、手付かず食事が残されている。じっと解決するまで動き出せない。これが「紀子の食卓」なのだ。17歳という年齢の少女が抱いた父親や周囲への不満が、常識的な理解を超え、こことは違う場所に、現実の嘘や矛盾が糾弾され、優しさに満ちた、もうひとつの世界を呼び込んでいく。
映画では、このもうひとつの世界は、「自殺クラブ」ではなく「自殺サークル」だという。年間3万人の自殺者を数える日本の現状を弱肉強食の世界に譬えて語る責任者も登場する。
最後の衝撃は、父・徹三が用意周到に念入りに仕掛けたサスペンス的展開となって、幸福なレンタル家族(徹三は父親、紀子と香が姉妹、クミコが妻の役を演じる)の夕食場面が映画的クライマックスとなる。そして、映画は惨劇を越えてラストシーンへと向かう。姉・紀子が抱いた、ここではない他の場所という「幻想」は消え、それは妹へ受け継がれる。
妹・ユカは姉・紀子への理解を深め、姉のコートを着て旅立つ。このラストは、それなりに納得し安堵して見終わる。幸福に見える家族に囲まれた17歳の女子高校生の行動が呼び起こした「現実の衝撃」には真実がある。妹は新たなもうひとつの世界に旅立つ。(06.10.22)
|
(キャスト)
吹石一恵
つぐみ
吉高由里子
光石研
公開年月日:2006.9.13
上映時間:159分
映画館:ケイズシネマ「K'scinema」(新宿)
|