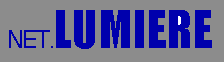
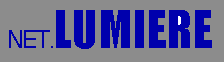
(スタッフ) 製作=俳優座映画放送 制作=佐藤正之 安部野人 原作=矢田喜美雄 脚本=菊島隆三 音楽=佐藤勝 美術=木村威夫 録音=紅谷愃一 照明=岡本健一 編集=井上治 |
(コメント) だから、この「シネマ・スペース」には、また、しばらくは、新しくつくられた映画が登場できないことになる。 今回は、すこしでも、映画スタッフの側に立った「映画空間」の新たな展開を試みてみたいと思うが、うまくいく保証はない。 いままでも、気になっていたのだが、映画を見た日と、この「コメント」を書き上げた日とのズレをわかるようしたい。何日かけて書いて、アップするときに再度確認しているが、基本は「書き上げた日」として記載しておくことにする。 ○まず、この映画はこの年に何故撮ることになったのだろうかということが、気になるのだが、製作が「俳優座映画放送」ということだけで、「そうか」と納得するしかないか。木村さんは、久々の「社会派」の映画になったと話していいるように、日本映画界にとっても、取り上げにくいテーマであるといえる。
監督と俳優座との繋がりは、72年に「忍ぶ川」(栗原小巻)、73年「朝やけの詩」(関根恵子)、74年「サンダカン八番娼館 望郷」(高橋洋子)、76年「北の岬」(加藤剛)、そしてこの「下山事件」となっている。
実は、社会派と印象づけたデビュー作の2本は見たいと思いながらも、未だに未見であり、熊井作品の全ては見てはいないのだが、89年の「千利休 本覚坊遺文」がわたしにはベストである。 それを見たあとに、「お吟さま」を見て感心したことを思い出し、今回は、この「下山事件」「お吟さま」の2本を見に出掛けてみることになった。
また、映画の原作は、元朝日新聞社の社会部記者が73年に「謀殺下山事件」というタイトルで刊行し、「下山は何者かによって殺された」と結論づけたものである。 65年の「日本列島」、原作が73年、80年のテレビ・ドラマ、そして、この映画ということになるのだが、「日本列島」「原作」が未見で、しかも、詳細な取材に基づく、この「テレビドラマ」も感心したことは確かだが、内容についての記憶は曖昧である。 さらに、木村さんが美術をやっている54年の山村聡監督「黒い潮」(ここでは「自殺説」だったという)も未見である。ちなみに、この「黒い潮」は、原作が井上靖であり、脚色は熊井作品同様に、菊島隆三である。
だから、撮影所が衰退していく中で、日本映画の仕事としては、それだけでも意義深く貴重である。
どうも、映画は、その謎解きに熱心に取り組む新聞記者(仲代)の執念が際だつ深刻ぶった演技が過剰であるという欠陥のために、最後まで、映画は「真実」に到達できなかったといわざるを得ない。
そして、時効が成立する15年目、貴重な「証言者」の「死」とともに真相は不明のままであるということか。 ここでの疑問は、映画のすべてが事実なのかフィクションなのかわかりにくく、事実を超えた「真実」を見ることができなかったことだ。 それは、戦中、戦後と生きてきた男(仲代)の「内面」がうまく伝わってこないということだ。これは、映画の制作過程でいえば、シナリオ段階の話しであり、キャスティングの問題である。
49年という時代の「新聞社」「事故現場」「デモする背景と場所」など、どうするか。ここで映画の「リアリズム」が問われる。
|
(キャスト) 公開年月日:1981.11.7 映画館:「映画美術監督 木村威夫の世界」川崎市民ミュージアム・映像ホール |