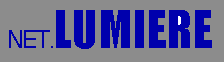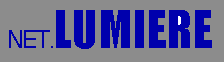|
(コメント)
○前に、「横浜ベティ」で見ている。期待しないで見ていたのだが、なかなかよくできているのに感心した。タイトルからはわからないが、利休役の志村喬が主役だと言ってもいい映画である。
○美術がしっかりし、大掛かりな映画だったことにあらためて驚かされるのだが、つくられた当時どうしても見たいと思える映画ではなかった。やはり、ここでも、当時、いま、なぜ「お吟さま」なのか理解できない。
このあたりの事情は、企画者、製作者に聞くしかないが、宝塚映画で時代劇を一本を撮りたいということだったのだろうか。受け手としての監督からいえば、それなりの予算で、これだけのスタッフ、キャストが選べるなら引き受けることになるのかと、今から思えば納得か。
うーん、どうだろう。前の「下山事件」でも言ったが、映画会社が衰退していく中で、「日本映画の仕事」として貴重であることは間違いない。
○まず注目したいのは、キャステイングとして、志村喬と三船敏郎との関係がある。秀吉を三船が演じるというのは意外だとだれでも思うだろうが、志村が扮する利休に無理難題をぶつけてくるのが、権力を持つ秀吉役の三船だということで、黒澤映画「七人の侍」を思い出しながら見ている。
○この映画は、志村さんが主役に見えることで、映画になっており、黒澤映画への映画人としてのオマージュにもなっている。そして、さらに、この秀吉が利休がじぶんの代理でおくった茶人、山上宗二が意見するのを怒って秀吉が宗二を手討ちにしたことを含めて、熊井監督は、利休役を三船敏郎で1989年に「千利休 本覚坊遺文」を撮っている。ちなみに、原作は井上靖、脚本は依田義賢、美術は木村威夫である。
○スケールの大きさは、「宝塚映画製作所のステージだけでは間に合わず、松竹傘下の京都映画撮影所や大映映画京都撮影所も動員して撮影された」さらに、「ひとつの部屋を分割し、その外側や内部をそれぞれ違った撮影所に作るという手法を採用したため、双方のマッチングに苦労した」とプログラムにある。日本映画の実状もうかがえるところだ。
○美術が十分に力を発揮し、目に見えるかたちが生まれてくる。役者たちをどこに立たせるか。そこに、どう光を当て、キャメラで撮るか。このシーンでの、ワンカット、ワンカットが監督の頭に「イメージ」として入っている。役者も含めて全スタッフが、その「イメージ」に向けて集中している。ヨーイ。そんな撮影現場を想像してみる。
○利休と秀吉の対立は十分見応えがある。そして、もうひとつ、高山右近(中村吉右衛門)の話がある。城を追われる右近に慕う多くの民衆たちといった光景が描かれるのだが、キリシタン大名「高山右近」の生きざまには驚かされる。
その妻子ある右近に、幼なじみでもあり許嫁でもあった吟(中野良子)は、利休の娘となり、堺商人(原田大二郎)に嫁いだ今も、右近に愛焦がれている。
秀吉と利休、秀吉と右近という対立の狭間で、その切ない純愛(信念)を貫きとおすということが、この映画のテーマである。利休、右近、吟の信念は、「家族」に寄り添われ見守られながら生きる。
○中野良子には、昔、東芝日曜劇場の単発ドラマで誰かの娘役で出ていたのを見て、強い印象を残したという記憶があるのだが、どうも、それ以降はかってはいない。
しかし、この「お吟さま」多少不満があるが、よくもわるくも「中野良子」のベストだと思う。
○ラストの高山右近の「なんたることだ」と叫ぶ台詞廻しと音楽の強調はいらない。(2003.2.8)
|