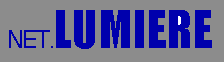
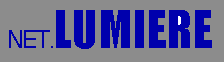
(スタッフ) 製作=アヌーシュカ・フィルム 音楽=ミシェル・ルグラン 衣装=ロランス・クレルヴアル 編集=フラソワーズ・コラン アニュス・ギユモ 助監督=ジャン・ピエール・レオー エレーヌ・カルガン クロード・オトナン=ジラール 使用音楽:ベートーベン/弦楽四重奏曲 第7番 第9番 第10番 第14番 クロード・ヌガロ/ジャズとジャワ 悲しきスクリーン(シルヴィ・ヴアルタン) |
(コメント) ラウル・クタールというキャメラマンとゴダールの共同作業としてみれば、あの90度に傾けたキャメラが捉えたドイツから小型飛行機で帰ってきた夫(パイロット)をむかえた妻が飛行機に向かう、そこに画面でいえば、向かって左に滑走してくる飛行機を捉えたシーンは、今見ても新鮮だ。これは、一度見たことがあると思わせるのは、クリス・マルケルの「ラ・ジュテ」を見ているからだろうか、それとも、予告編などで、一度は見ているのだろうか。また、ネガ・フィルムのシーンをさし挟んでみせたシーンも含めて全編、通常の映画とは違って見えることとラウル・クタールの関わりを思う。 女性の裸体を部分的にしか見せないことの「嫌らしさ」とエロティシズムの「普遍性」と、女性の下着の進歩が当時から現在は格段の進歩を遂げているとしてもカタログを見る女性の心理や関心の持ち方など、すべての「意味」が何も変わっていないことに驚く。 女中のおしゃべりや、女学生の会話に耳を傾けるというシーンには、ゴダールが何に興味を持っているのか、そして映画の意味も、そこに隠されているのだろうと、もう少し立ち入ってみたくなるが、ゴダールは、その手の内は、なかなか見せてはくれない。 映画誌「映画芸術」の巻頭の「シネマ・エロティシズム」という「グラビア」でこの「恋人のいる時間」の何枚かのカットは、十代の頃見ていることは確かだ。ついでに、大きなパンツ、大きなブラジャーという女性の下着は、このヒロインが、生活の豊かさの中で、夫と子供を持ち、愛人にも思いを寄せる行為と共に、この64年というフランスの時代を語ることになるのか。また、愛人との密会を隠すためのカモフラージュとして見せる、タクシーの乗り継ぎやホテルに向かう愛人とふたりで、人目を気にした「逢いびき」としての仕草や行動は、まぎれもなく「ゴダール映画」であり、映画的な「自由」と「遊び」を語っている。(2003.5.26) 「恋人のいる時間」(ジャン=リュック・ゴダール)ⓠ「カイエ・デュ・シネマ」誌第159号(1964.9月号)「映画をつくるやり方はいくつかある。ジャン・ルノワールやロベール・ブレッソンがするように、音楽をつくるようにつくるやり方。セイゲイ・エイゼンシュテインがするように、絵画をつくるようにつくるやり方。シュトロハイムがするように、サイレント時代にトーキーの小説を書くようにつくるやり方。アラン・レネがするように、彫刻をつくるようにつくるやり方。そして、ソクラテスがするように、つまり私が言いたいのは、ロッセリーニがするようにということだが、ただ単に哲学をつくるようにつくるやり方。要するに映画は同時にすべてでありうる、つまり裁くものであると同時に裁かれるものでありうるということである。 |
(キャスト) マーシャル・メリル 公開年月:1965.2 映画館:横浜・関内アカデミー2「映画の学校PART1 ⓠプログラムに、この映画を撮ったころに「カイエ・デュ・シネマ」誌に、ゴダールが書いた一文が掲載されている。一部を引用しようと思ったが、全文になってしまった。「ゴダールの映画史」を見たときにも感じ入ったままゴダールとゴダール映画についてうまく語れないという事態をうまく解決できないまま、いま、また同じ場面に遭遇している。「ゴダール」はいつまでも課題であり続けるしかない。 |