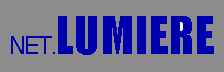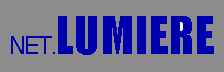|
(スタッフ)
製作国=フランス/スイス
製作=アラン・サルド
ルート・ヴアルトブルゲール
脚本=ジャン=リュック・ゴダール
撮影=クリストフ・ポロック
|
(コメント)
圧倒的な驚きとともに感動させられるのは、後半のカラーになっていくところからだろう。岩と波、そして青い海と空。色が凄い。極彩色の色が塗られて絵の具の固まりかと思わせ、画面が映像として動き出す。ここに、ストップ・モーションとスロー・モーションが見るものには、そうとは感じさせずにちりばめらてれいる。この第二部が、デジタル・ビデオで撮られていることを後で知るのだが、いくつかの映像が重ねられている効果も合わせて、「映画史」後の成果であり、まさに、またもやゴダールに「21世紀の映画表現」として、先を越されてしまったことになるのか。
映画的引用としては、「マトリックス」のポスターが映画館に見える。ロベール・ブレッソンの「シネマト・グラフ覚書」、老夫婦のレジスタンスの映画化を目論むアメリカの映画会社が「スピルバーグ社」になっている。文学からは、サルトルのイルミナシオン。哲学からはベルグソン。
映画をつくろうとしているエドガーは、若い芸術家でもあり、二部では、2年前からシモーヌ・ヴェイユのカンタータをつくろうとしていたこともわかるのだが、いま、パリでは、「愛について」の映画を企画し、ヒロイン役を探すが、なかなか気に入ったイメージが合わない。エドガーは既成の舞台俳優ではなく、シモーヌ・ヴェイユのような思想性のある女性をイメージしている中で、2年前に会っている女性を思い出す。アプローチするが、子持ちで清掃の仕事もしているなどで、エドガーには取り合わない。高速道路の下で、背を見せてふたりは話す。これは、後でわかるのだが、エドガーは、一番に彼女の声が気に入っている(ゴダールのキャスティングでも、「その声」が第一に選ばれている)。
しかし、映画は実現しないまま、彼女は病気で亡くなる。暗いモノクロ画面だが、端正なモノクロで、ピアノとチェロのゆったりとした哀調のある曲が淡々と流れ音楽も素晴らしい。また、シャッターが開けられていく場面は、映像のコントラストと変わっていく音楽が効果的で息をのむ。どうも、いま、どういうシーンがあったかが、うまく思い出せないのだが、この音楽と映像だけでも、特筆に値する名場面である。ゴダール映画は、内容よりも、まず映像に感動するという希有な映画でもある。もちろん、内容も重要であるが、そこまで理解するには、どうも映画を何度も見て、シナリオの採録を手に入れることが必要だ。それは、外国語の映画ということを超えて、ゴダール映画の特性だといえるだろう。
それは、さまざまな引用が、ゴダールの言葉で語られることでの混乱、言葉どおり受け取っていいのか戸惑いながら、言葉が概念的にしか語られない。映画とは何であるかということに精通しているゴダールが、支離滅裂な映画をつくってしまうことの意味がわからない。黒い画面も言葉が重ねられる。われわれは、字幕を読むという結果になるのだが、どうも、ここでリッセットがかかる。フィルムを繋ぐ、編集の問題でもある。(2003.6.3)
|
(キャスト)
ブルーノ・ビュッツリジュ
セシル・カンプ
ジャン・ダヴュー
フランソワーズ・ヴェルニー
公開年月日:2002.4.13
映画館:横浜・関内アカデミー2「映画の学校PART1
J=L・ゴダール+2」
|