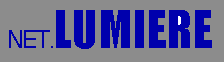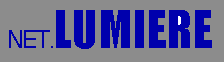|
(スタッフ)
製作国=日本
製作=独立映画
製作=伊藤武郎・松本酉三・絲屋寿雄・山田典吾・能登節雄・嵯峨善兵・柏倉昌美・浅野龍麿・若山一夫
|
(コメント)
独立映画株式会社の旗揚げ作品として、三人の監督の短編を集めてオムニバス映画になっており、個々の映画は独立している。
第1話 「花賣り娘」(吉村公三郎監督=新藤兼人脚本)・乙羽信子
撮影・宮島義勇 美術・丸茂孝
近代映画協会のスタッフでつくられている。短い話しでなんとか映画しようということだろうが、さすがにうまく映画にしている。夜のバーや路上で花を売る娘たちがいるが、客たちは煩がって相手にしない。貧しい家庭を助けるために健気に働く花売り娘たち。二階にあがったところにある小さなバーで働くマダム役が乙羽信子。男の借金を返すために、金の融通をこの店のオーナーである割腹のいい男に頼んでいるようだが、オーナーは金を用立てる条件に、暗に彼女の体を求めていることが、店を閉めてあとのふたりのやりとりでわかる。陰鬱の空気が淀む。ここで、得意の雨が降ってくる。カメラは外へ。バーの前の路上に停められた車に、強い勢いで雨が降っている。運転席にはオーナーが見える。車に乗り込もうとする乙羽は、雨を避けるようにビル陰に、売れない花を抱えて立っている娘を見て、その花を全部買う。娘は喜んで帰る。娘の家の前に人だかりがあり、家族ものが亡くなったことがわかる。娘の手に持たれていたイチゴが落ちる。それからふたりの後日談。花売り娘は、乙羽に礼を言いたくて、乙羽の住む部屋を訪ねあててやってくる。乙羽は寝ていた布団を畳んで向かい入れる。ほんとによくきてくれたと喜ぶ乙羽。塞いだ気持ちが晴れていく、ふたりには心暖まる「希望」が湧いてくるといったそんな映画であるが、ちょっと無理もあるかな。
(第2話)とびこんだ花嫁(今井正監督・新藤兼人脚本)・香川京子
撮影・中尾駿一郎 美術・川島泰造
今井正作品について書くのははじめてだと思ったが、「キクとイサム」についてふれたことがあることを思い出した。これは、やはり今井正の常連のスタッフでつくられている。貧しい農村から都会に出て、工場に勤め、月給取りになっている次男坊(内藤武敏)に、嫁(香川京子)が送り出せれてきて慌てるという話しである。当時は、この「月給取」というのは、安定した職のイメージがあって羨ましがられたのだが、この主人公は、ひとりで食べるのもやっとという貧しい生活であることからも、とにかく帰ってもらおうとる。しかし、背景には、人減らし的な経済事情があるのだが、内藤の母も、香川の兄も、そして、本人も、この結婚に充分に納得しているし、二人は幼なじみでもあることからも、気持ちが通じ合っていく。「わたし貧乏には慣れているから大丈夫」と香川が言う。働く工場の昼休みや川崎駅前など当時の様子が描かれ、同僚とのコミカルな会話や香川を捜す内藤を追う映像などテンポよく展開させる。同監督作品の「どっこい生きている」(未見)タイトルを思い出したが、当時の世相が垣間みることができる。ここには、貧しいが生きる明るさがある。
(第3話)愛すればこそ(山本薩夫監督・山形雄策脚本)・山田五十鈴/久我美子 撮影・伊藤武夫
三人の監督の個性が十二分に発揮されていると言えるだろう。脚本、撮影など気心の知れたスタッフで映画を創って見せる。こうした短編でも、役者もしっかり豪華なものになっている。今回の上映チラシに、「スタッフ、キャストらも手弁当で参加」とあるように、この映画づくりには、「独立映画」の旗揚げという映画運動への参加という意識と、この映画で言えば、山本薩夫を中心とした映画づくりに賛同したということなのだろう。それは、映画の内容については、演じるもの、撮影をするもの、美術や音楽を担当するものというプロ意識で役割を担うということで関わるということなのだろう。
いま、わたしには、この映画の内容についての疑問が、この映画の創られ方や映画運動という意識と深く関わっていることだと思える。このことは、その後日本映画つくられた方のひとつ流れを象徴している。それは、1953年、54年にピークを迎えた独立プロの映画群の検証が必要なのだが、この映画を語ることで、その一端を見ることが可能だと思う。
では、この映画の展開を見ていこう。優秀な大学に通っている自慢の息子が、学生運動に参加し警察に検挙され留置場に入れられていることで、家族に大きな波紋を投げかけている。家族は母と姉と妹の4人暮しである。母(山田五十鈴)は近所で「あんなに息子自慢していたのに」と白い目で見られている。姉は結婚を控え狼狽えている。妹は兄は正しいと主張している。そこへ母の弟(山村聡)が手助けに現れる。それは、すべて常識的に穏便に事を納めようと主張し実行しようとする。姉は家を出て許婚者と暮らすこと、弟は罪を認めればすぐに留置場を出れるのだがらそうすればいいと勧める。姉は切羽詰まっている。ふたりで住む格安の部屋が見つかっている、このチャンスを逃したくないとも言う。母は息子を信頼し信じたいと思っている。大学の偉い先生も、息子のことを正しいといってくれていると弟の意見には賛同しかねている。ここでは、家族は貧しいく倹しい生活が窺える中で、この息子は、この貧しさの責任を社会の矛盾として捉え、学生運動に参加し信念を持って闘っている。
映画は、この家族の深刻なやりとりをする茶の間のシーン、留置場での母との面会シーン、そこですれ違う女学生(久我美子)、じぶんの経験から残された家族への支援も忘れてはならないと話すシーンと続き、母とその女学生は、留置場からの帰り道、肩を並べて歩きながら親しく会話を交わす。女学生は明るく現気に母親を励まし映画は終わる。ここでは、運動に参加し、闘うこと連帯することが正しいと信じているものと、そのことは反社会的で世渡りには大きな支障があるという一般常識的認識との葛藤を描かれていると言えるとしても、どうしても左翼の運動に強くシンパシーを持つ基調が色濃く窺えることは、この映画の持つ致命的な欠点である。それは深みのないプロパガンダ映画にしかなっていないといえるが、それにしては、山田五十鈴、山村聡、久我美子と豪華なキャスティングであり、役者が垣間見せる表情は豊かである。(2005.2.20)
|
公開年月日:1955.01.22
映画館:川崎市市民ミュージアム
|