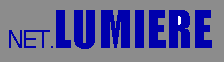
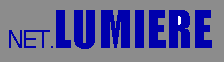
(スタッフ) 製作=東映 今村プロダクション 製作=友田二郎 美術=吉野尹孝 稲垣尚夫 録音=紅谷愃一 照明=岩木保夫 編集=岡安肇 スチール=石黒健治 |
(コメント) また、この70歳を過ぎるとわが子に背負われ楢山に捨てられるという風習の惨さを描くことで、今村昌平は何をこの映画で見せたいのか、よくわからなかったというのが、これも最初に見たときの感想である。しかも、その映画化としては、すでに木下恵介の実験的意欲作がある。それは、舞台装置の中へ押し込むことで、伝承性を昇華し、つくりものであるという映画表現の力を思う存分に発揮して見せた傑作であった。それに対して、この「楢山節考」には、映画表現に自覚的な意識を持つ今村昌平の新しさが感じられなかった。
だからこそ、この映画のクライマックスは、楢山に行くときに雪が降るという言い伝えどおりに、おりんを山に置き去りにするときに雪が降り出すというシーンということになる。下山する辰平。あたりの山の風景が一気に雪化粧される。喜ぶ辰平は、「よかったな。本当に雪になったな。」とおりんに言うために戻る。おりんは正座し一心に拝んでいる。早く行けと手で辰平を追い払うおりん(けして振り返ってはならないという掟がある)。というように描かれる。見るものは、この一気に雪が降り積もって山の景色が一変するという表現に感動する。あえて言えば、これが映画の映像表現であって、単なる自然を撮った映像には感動はしない。
しかし、どうしても、これらの表現が図式的・羅列的で上滑りし、自己模倣に陥っていると感じざるを得ないのだ。反権力を志向し根源的な共同体論を展開すべく映画「神々の深き欲望」1968が持った時代性と殺気立つ熱気を映画作家・今村昌平自身としても越えることができない。(2005.9.29) (セプテンバー11で人間のかたちのまま、蛇になった男が鼠を銜えて呑み込むシーンがあるが、同様な蛇の実写のシーンがインサートされていた。) |
(キャスト) あき竹城 公開年月日:1983.4.29 映画館:川崎市民ミュージアム「今村昌平の世界」 |